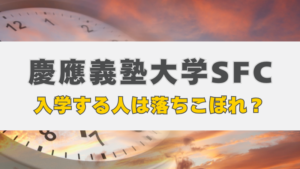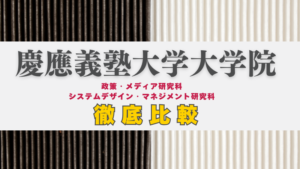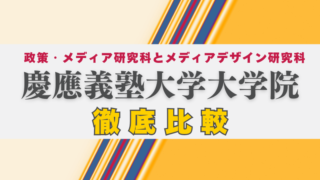
- 1. なぜ今、政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科が注目されるのか?
- 2. 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の概要と特徴
- 2.1.1. 1.教育理念と目指す人材
- 2.1.2. 2.研究領域とプログラム
- 2.1.3. 3.教育の特徴
- 3. 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD)の概要と特徴
- 3.1.1. 1.教育理念と目指す人材
- 3.1.2. 2.研究領域とコース
- 3.1.3. 3.教育の特徴
- 4. 政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD):どこが違うのか?
- 5. あなたはどちらの研究科に向いているか?
- 6. KOSSUN教育ラボのサポート体制
- 7. 最後に
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「慶應義塾大学大学院に進学したいけれど、SFCの政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD)、一体何が違うんだろう?」
もしあなたがそう考えているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。総合型選抜専門塾KOSSUN教育ラボの教務担当として、これまで多くの大学院進学希望者の相談に乗ってきた経験をもとに、政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD)の教育理念、研究領域、特徴、そしてどのような方がそれぞれの研究科に向いているのかを徹底的に解説します。
この記事を読むことで、あなたは政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科の違いを明確に理解し、ご自身の興味関心や将来の目標に合致する研究科を選ぶための重要な判断材料を得られるでしょう。
なぜ今、政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科が注目されるのか?
現代社会は、テクノロジーの急速な進化、グローバル化の進展、そして複雑化する社会課題に直面しています。このような時代において、既存の学問領域の枠を超え、新しい視点と方法論で課題解決に取り組む人材が強く求められています。
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)に設置された政策・メディア研究科と慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科は、まさにそのような時代が求める人材を育成するために設立されました。両研究科は、それぞれ独自の理念とカリキュラムを持ち、社会の変革を担うリーダー、イノベーターの育成を目指しています。
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の概要と特徴
政策・メディア研究科は、政策科学、環境科学、情報科学を融合し、複雑な現代社会の課題に対して、学際的かつ実践的なアプローチで研究・教育を行うことを目的としています。
1.教育理念と目指す人材
政策・メディア研究科は、「複合的な課題に向き合い、常に社会との接点を持ちながら調査研究を遂行し、その成果を人々の暮らす現場へと届ける」ことを使命としています。既存の専門分野にとらわれず、多様な視点を取り入れながら研究を発展させ、新しい社会システムやテクノロジーの創造に貢献できる人材の育成を目指しています。
政策・メディア研究科が育成を目指す人物像は、
- クリエイティブで実践力を持った人材: 既存の枠にとらわれず、新しい発想で課題解決に取り組み、社会実装まで実現できる力を持つ人材。
- 分野融合の知見を活かし、新しい仕組みを発案し、新しい価値を創り出せるイノベーティブな人材: 異なる専門領域の知識や視点を統合し、社会に新たな価値を生み出すことができる人材。
- 専門領域にとらわれず基礎体力と実践力があってグローバルな舞台でも地球規模で活躍できる人材: 幅広い知識と実践的なスキルを持ち、国際的な視野で地球規模の課題に取り組むことができる人材。
2.研究領域とプログラム
政策・メディア研究科は、以下の8つのプログラム専門領域を設置し、学際的な研究・教育を行っています。
- グローバル・ガバナンスとリージョナル・ストラテジー(GR)
- ヒューマンセキュリティとコミュニケーション(HC)
- 政策形成とソーシャルイノベーション(PS)
- 認知・意味編成モデルと身体スキル(CB)
- 環境デザイン・ガバナンス(EG)
- エクス・デザイン(XD)
- サイバーインフォマティクス(CI)
- 先端生命科学(BI)
これらのプログラムは、社会科学、自然科学、情報科学といった多様な学問領域を横断しており、すべての大学院生はいずれかのプログラム専門領域に所属し研究を進めることになります。
3.教育の特徴
政策・メディア研究科の教育には、講義だけでなく、実践を重要視する P.B.L.(Project Based Learning)があります。PBLでは、学生が主体的に問題を発見し、解決策を提案し、社会実装を目指す実践的な研究活動を行います。多様な専門分野の教員から構成される研究プロジェクトに学生が参加し、実践を通して課題解決能力を養います。
また、国内外の大学・研究機関との連携も積極的に行っており、グローバルな視点と実践力を養うための多様な機会が提供されています。英語を共通語とする国際コースも設置されており、海外からの留学生も多く在籍する国際的な研究環境が特徴です。
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD)の概要と特徴
メディアデザイン研究科(KMD)は、「メディア・イノベータ」の育成をミッションとし、現実社会の課題に対し、あるべき未来を想像しながら、人と人、人類と我々を取り巻く環境とを新たな形で繋ぎ、未来の社会を切り拓く「メディアデザイン」の実践と研究を行うことを目的としています。
1.教育理念と目指す人材
メディアデザイン研究科(KMD)は、イノベーションを自ら生み出し社会に向けて価値を創出する能力を持つ「メディア・イノベータ」の育成を使命としています。メディア・イノベータは、特定の分野や国境の枠を超えてグローバルに活動し、創造社会を先導していくことが期待されています。
KMDが育成を目指す人物像は、
- 現実社会の課題に深く向き合い、未来を構想できる人材: 社会のニーズや課題を的確に捉え、新しい技術やデザインを用いて未来の社会像を描き出すことができる人材。
- 多様な専門性と視点を統合し、革新的な価値創造を主導できる人材: テクノロジー、デザイン、ビジネス、社会科学など、多様な分野の知識を融合し、これまでにない新しい価値を生み出すことができる人材。
- グローバルな視点を持ち、異文化を理解し、国際的な舞台で活躍できる人材: 異なる文化や価値観を持つ人々を理解し、尊重しながら、国際的なプロジェクトを推進し、グローバル社会に貢献できる人材。
2.研究領域とコース
メディアデザイン研究科(KMD)は、特定の専門分野に限定されず、学生一人ひとりの興味関心に基づいた多様な研究テーマを支援しています。
- インタラクションデザイン: 人とコンピュータ、人と人との新しいコミュニケーションのあり方をデザインする研究。
- サービスデザイン: テクノロジーを活用し、人々の生活を豊かにする新しいサービスをデザインする研究。
- コンテンツデザイン: 映像、音楽、ゲーム、ウェブコンテンツなど、多様なメディアを用いた新しい表現や体験をデザインする研究。
- プラットフォームデザイン: ソーシャルメディア、IoTプラットフォームなど、新しい社会インフラをデザインする研究。
- ウェルビーイングデザイン: 人々の幸福感や健康を向上させるためのデザイン研究。
3.教育の特徴
メディアデザイン研究科(KMD)の教育は、チームベースのプロジェクトを核として展開されます。学生は多様なバックグラウンドを持つ仲間とチームを組み、現実社会の課題に対して、REFLAME(問い直し)→MAKE(プロトタイピング)→DEPLOY(実装)→IMPACT(影響評価)というプロセスを繰り返しながら、革新的なソリューションを創り出す実践的な研究活動を行います。
また、多様性を重視しており、国籍、専門性、年齢など、様々な背景を持つ学生が集まることで、刺激的な学習環境が生まれています。国際交流も盛んで、海外の大学院との連携プログラムやイベントも多数実施されています。さらに、シリコンバレーと東京での滞在プログラムを通じて、異なる文化やビジネススタイルを体験し、国際感覚とイノベーションマインドを養う機会も提供されています。
政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD):どこが違うのか?
政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD)は、どちらも学際的で実践的な研究・教育を行う大学院ですが、その焦点とアプローチには明確な違いがあります。
| 項目 | 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 | 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) |
|---|---|---|
| 教育理念 | 複合的な社会課題に対し、政策科学、環境科学、情報科学を融合した学際的アプローチで解決策を探求し、社会実装を目指す。 | 現実社会の課題に対し、未来を構想し、テクノロジーとデザインを用いて革新的な価値を創造する「メディア・イノベータ」を育成する。 |
| 研究の焦点 | 政策、環境、情報という3つの科学を基盤とし、社会システム、ガバナンス、環境問題、情報技術など、幅広い領域を対象とする。 | メディアデザインを核とし、インタラクション、サービス、コンテンツ、プラットフォーム、ウェルビーイングなど、より具体的なデザイン領域に焦点を当てる。 |
| 主なアプローチ | プロジェクトベースドラーニング(PBL)を通じて、学生が主体的に問題発見・解決に取り組み、社会実装を目指す実践的な研究を重視する。多様な専門分野の教員による指導と、国内外の連携を重視する。 | チームベースのプロジェクトを通じて、REFLAME→MAKE→DEPLOY→IMPACTのサイクルを実践し、革新的なソリューションを創出する。多様性、国際交流、シリコンバレーとの連携などを重視する。 |
| 目指す人材像 | クリエイティブで実践力のある人材、分野融合型のイノベーター、グローバルに活躍できる人材。 | 未来を構想できる人材、多様な専門性を統合できるイノベーター、グローバルな視点を持つ人材。 |
| キーワード | 学際性、複合的な課題解決、社会実装、政策科学、環境科学、情報科学、プロジェクトベースドラーニング、グローバル連携。 | メディアデザイン、イノベーション、チームワーク、プロトタイピング、実装、多様性、国際交流、シリコンバレー。 |
あなたはどちらの研究科に向いているか?
政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD)のどちらに進むべきか迷っている方は、以下の点を考慮して、ご自身の興味関心や将来の目標と照らし合わせて考えてみてください。
こんなあなたは政策・メディア研究科向き
- 社会の構造や仕組み、政策のあり方に関心がある。
- 環境問題やエネルギー問題など、地球規模の課題解決に貢献したいと考えている。
- 情報技術を社会の発展や課題解決に応用することに興味がある。
- 多様な学問分野を横断的に学び、幅広い視野を持ちたい。
- 自分で問題を発見し、主体的に解決策を探求したい。
- 研究成果を社会実装することに強い意欲がある。
こんなあなたはとメディアデザイン研究科(KMD)向き
- 新しいテクノロジーやメディアを活用した革新的なサービスやコンテンツの創造に興味がある。
- 人々の生活をより豊かにする新しいデザインやインタラクションを追求したい。
- 多様な専門性を持つ仲間と協力して、チームでプロジェクトを進めることに魅力を感じる。
- プロトタイピングや実装を通して、アイデアを形にすることに情熱を持っている。
- グローバルな視点を持ち、国際的な舞台で活躍したいと考えている。
- 既存の枠にとらわれず、新しい価値を生み出すイノベーターを目指したい。
KOSSUN教育ラボのサポート体制
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜で SFC を目指す皆さんを総合的にサポートしています。
- SFCの入試情報提供: SFCのアドミッション・ポリシーや入試傾向、面接対策など、SFCの入試に関する情報を詳しく解説します。
- 書類作成指導: SFCの入試で課される志望理由書や自由記述などの書類作成を、個別に丁寧に指導します。
- 面接対策: SFCの面接官の視点に立った実践的な指導で、自信を持って面接に臨めるようにサポートします。
- 学習計画:一人ひとりに合わせた学習計画を作成します。
KOSSUN教育ラボで対応している対策の詳細は公式ホームページをお確かめください。
最後に
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科とメディアデザイン研究科(KMD)は、それぞれ異なる魅力と特色を持つ研究科です。この記事を通して、それぞれの違いを理解し、ご自身に合った研究科を見つけるための一助となれば幸いです。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。