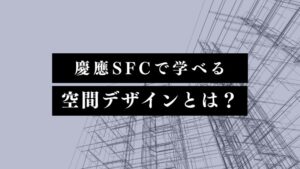こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「慶應義塾大学で経済学を学びたい」と考えたとき、多くの受験生は三田キャンパスの経済学部を思い浮かべるでしょう。しかし、湘南藤沢キャンパス(SFC)でも、非常に実践的で未来志向の経済学を学ぶことができます。
ただし、SFCには「経済学部」という看板はありません。では、SFCの学生はどのように経済学を学び、どのような専門性を身につけていくのでしょうか?
この記事では、2024年度にSFCで開講されている「研究会(プロジェクト)」のリストを徹底的に分析し、SFCにおける経済学の学びのユニークな実態と、それが伝統的な経済学部とどう違うのかを明らかにします。
大前提:SFCに「経済学部」はない。経済学は「問題解決のツール」である
SFCの最も重要な特徴は、決まった「学部・学科」のカリキュラムに縛られないことです。学生は、自らが抱く「問題意識」を軸に、それを解決するために必要な学問分野を、まるで道具箱からツールを取り出すように、主体的に学んでいきます。
この環境において、経済学は「学ぶこと」自体が目的ではなく、現実社会の複雑な問題を分析し、解決策を導き出すための強力な「思考のツール」であり「分析手法」として位置づけられています。その学びの中心となるのが、学生が所属し探求活動を行う「研究会」です。
研究会リストから読み解く、SFC経済学の3つの特徴
実際に開講されている研究会のラインナップを見ると、SFCにおける経済学の学びの具体的な特徴が浮かび上がってきます。
特徴1:徹底した「データ駆動」×「問題解決」志向
SFCの経済学は、理論を学ぶだけで終わりません。現実のデータを用いて、自らの手で社会を分析することに重きを置いています。
経済学とデータで読み解く現代社会のリアル(応用ミクロ計量経済学の実証分析)計量経済分析
これらの研究会名が象徴するように、SFCでは「計量経済学」が非常に重視されています。これは、統計学的な手法を用いて経済データを分析し、政策の効果や社会現象の因果関係を科学的に検証する学問です。SFCの学生は、抽象的な理論を学ぶだけでなく、「この政策は本当に効果があったのか?」「この社会問題の原因は何か?」といった問いに対し、データという客観的根拠をもって答えを探す訓練を徹底的に行います。
特徴2:「ビジネス・金融・政策」に直結した実践的な学び
SFCの経済学は、学問のための学問ではなく、社会の第一線で活かすことを強く意識しています。
デジタル新時代の経済とビジネスSeminar on International Economy and Finance / 国際経済・⾦融研究会コーポレートファイナンスとESG経営アントレプレナーシップと経営変化する日本型雇用と労働政策の未来
これらの研究会からは、国際金融、企業財務(ファイナンス)、経営戦略、労働政策といった、極めて実践的なテーマに直接取り組んでいることがわかります。新しいビジネスモデルの創出や、グローバルな金融市場の分析、企業の社会的責任(ESG)といった現代的な課題に対し、経済学の視点からアプローチしていきます。
特徴3:テクノロジー、社会、地域研究との「学際性」
SFCの真骨頂は、経済学を一つの閉じた学問としてではなく、他の多様な学問分野と融合させて学ぶ点にあります。
- テクノロジーとの融合:
デジタル新時代の経済とビジネス、データドリブンによるスマート都市・地域の構築 - 社会学・人口学との融合:
人口・社会動態の探究、ソーシャルセクターとヒューマンサービスの社会学 - 地域研究との融合:
韓国・北朝鮮の政治・経済・社会、現代東南アジア研究、マーケティング・コミュニケーション / 地域デザイン
例えば、「なぜこの地域は衰退しているのか?」という問いに対し、経済学的な分析だけでなく、その地域の歴史や文化、住民のコミュニティ、最新のIT技術の活用可能性など、複数の視点を掛け合わせて解決策を探ります。これが、単一の経済学部では難しい、SFCならではのダイナミックな学びです。
SFCで経済学を学びたいあなたへ
もしあなたが、SFCで経済学を学びたいと考えているなら、次のような視点を持つことが重要です。
- 「何を」学びたいか、ではなく「経済学を“使って”何をしたいか」 「経済学の理論を学びたい」という志望動機だけでは不十分です。「地域格差の問題を、計量経済学の手法を用いて分析し、持続可能な地域産業を創出する政策を提言したい」というように、解決したい社会問題と、そのためのツールとしての経済学を結びつけて考えることが求められます。
- 知的好奇心のアンテナを広く張る 経済学だけでなく、テクノロジー、デザイン、政治、歴史、言語など、一見関係ないように思える分野にも興味を持ち、それらを経済学とどう結びつけられるかを考える姿勢が、SFCの環境を最大限に活かす鍵となります。
最後に
SFCにおける経済学の学びは、伝統的な経済学部とは一線を画します。それは、データという武器を手に、ビジネス、政策、テクノロジーといった多様な領域を横断しながら、現実社会の複雑な問題解決に挑む、ダイナミックで実践的な学問です。
もしあなたが、既存の枠組みにとらわれず、経済学を社会をより良くするための強力なツールとして使いこなしたいと願うなら、SFCはあなたにとって最高の学びの場となるでしょう。
KOSSUN教育ラボは、あなたの「SFCで学びたい」という熱い想いを、最も効果的な形でSFCに届けるお手伝いをします。まずは一度、無料相談にお越しください。あなたの個性や強みを活かし、慶應SFCへの合格を掴み取るための具体的なロードマップを一緒に考えていきましょう。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。