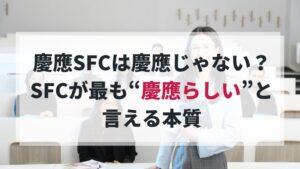- 0.1. STEP 1:SFCの「研究会」は、ただのゼミじゃない — その本質を理解する
- 0.2. STEP 2:あなたの興味はどこにある? 研究会マップ(分野別カテゴリー)
- 0.2.1. ① テクノロジーで未来を実装する
- 0.2.2. ② ビジネス・社会のデザインを探求する
- 0.2.3. ③ グローバルな課題に挑む
- 0.2.4. ④ 建築・都市・地域をデザインする
- 0.2.5. ⑤ 生命・健康・身体の謎に迫る
- 0.2.6. ⑥ 人間と文化・コミュニケーションを深く知る
- 0.3. STEP 3:自分にぴったりの研究会の見つけ方 — 3つのアクション
- 0.3.1. アクション1:公式サイトとシラバスを「探検」する
- 0.3.2. アクション2:オープンキャンパスやORFで「直接」話を聞く
- 0.3.3. アクション3:自分の「問題意識」を「仮説」としてぶつけてみる
- 0.4. 最後に
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「慶應SFCに入ったら、どの研究会に入ればいいんだろう?」 「自分の興味に合った、おすすめの研究会を知りたい」
SFCを目指す受験生、そして入学を控えた新入生にとって、「研究会」選びは、SFCでの学びの方向性を決める、最も重要で、最もエキサイティングな選択です。
しかし、SFCには150を超える多様な研究会が存在し、その選択肢のあまりの多さに圧倒されてしまうかもしれません。この記事では、「これこそが絶対におすすめ!」という一つの正解を提示するのではなく、広大な知の海の中から、あなたにとって最高の「おすすめ研究会」を見つけ出すための方法を、具体的な研究会を例に挙げながら徹底的に解説します。
STEP 1:SFCの「研究会」は、ただのゼミじゃない — その本質を理解する
まず、SFCの「研究会」が、一般的な大学の「ゼミ」とは全く異なるものであることを理解しましょう。公式サイトには、その本質が次のように記されています。
SFCでは、「問題が与えられ、正解を教わる」のではなく「何が問題かを考え、解決方法を創出する」ことができる、「未来の先導者」を育成...。それを実践するための「研究会」は単なるゼミのような勉強グループではなく、企業との共同研究や官公庁からの委託研究など、先端的な研究活動が数多く行われています。
つまり、研究会とは「社会と直結した、最先端の研究開発チーム」なのです。教員をリーダーに、大学院生や学部生が学年の垣根なく対等なパートナーとして参加し、現実社会の課題解決に挑みます。学生は、その中で高度な専門性を身につけ、自らの卒業プロジェクトを、未来への「自分自身のプロポーザル(提案書)」として完成させていきます。
STEP 2:あなたの興味はどこにある? 研究会マップ(分野別カテゴリー)
150以上の選択肢を前に、まずは自分の興味がどの方向にあるのか、大まかな地図を掴むことが重要です。ここでは、2024年度に開講されている研究会を、6つの大きなカテゴリーに分けて紹介します。あなたの心が動くキーワードを探してみてください。
① テクノロジーで未来を実装する
AI、IoT、自動運転、ロボット、VR/AR、3Dプリンティングといった最先端技術を、自らの手で創り出し、社会をどう変えていけるかを探求する領域です。
- 代表的な研究会:
スマートモビリティ〜自動運転車や自動運転バスを創ろう〜ゼロから作るDeep LearningAQUA: 量子計算機と量子ネットワークソーシャルクラウドロボティクス次世代パーソナル・コンピューティングの創成
② ビジネス・社会のデザインを探求する
新しいビジネスモデルや企業の経営戦略、経済や金融の仕組み、そしてより良い社会を創るためのソーシャルイノベーションまで。社会を動かす「仕組み」をデザインする領域です。
- 代表的な研究会:
経営研究:優れた経営の実践と普遍的知見の探求経済学とデータで読み解く現代社会のリアルコーポレートファイナンスとESG経営ソーシャルイノベーション:「ソーシャルマーケティングと価値共創」アントレプレナーシップと経営
③ グローバルな課題に挑む
国際関係、安全保障、SDGs、地域紛争、多文化共生など、国境を越えて広がる地球規模の課題に、多様な視点からアプローチする領域です。
- 代表的な研究会:
国際安全保障とグローバルガバナンスxSDG田中浩一郎研究会(現代中東政治研究)日本における「難民・移民」と多文化共生アメリカ政治外交研究:デモクラシー、メディア、選挙
④ 建築・都市・地域をデザインする
建築やランドスケープといった物理的な空間から、そこに住む人々のコミュニティ、持続可能なまちづくりまで。私たちが生きる「場」を豊かにデザインする領域です。
- 代表的な研究会:
ランドスケープ研究パーティシパトリー建築・都市・コミュニティデザインデータドリブンによるスマート都市・地域の構築マチモノツクリ研究会 ~3D/4Dプリンティングを活かした「都市エレメント」のデザイン~場のチカラ プロジェクト(まちに還すコミュニケーション)
⑤ 生命・健康・身体の謎に迫る
ゲノム科学や脳科学、スポーツ科学、メンタルヘルスなど、人間という存在の根幹である「生命・健康・身体」の謎を、科学的に探求する領域です。
- 代表的な研究会:
ゲノム生物学(先端生命科学)身体運動の神経科学 〜脳と身体をひとつの"システム"として捉える〜ヘルスサイエンス(健康・幸福な街づくり)脳情報の計測と解析食とフードサイエンス
⑥ 人間と文化・コミュニケーションを深く知る
言語、歴史、宗教、ジェンダー、教育、アートなど、人間が築き上げてきた文化や社会、そしてコミュニケーションの本質を、多様な切り口から深く探求する領域です。
- 代表的な研究会:
イスラーム研究オーラル・ヒストリー―「聞く力」で未知を拓く―言語と学習の認知科学ジェンダーについて話したい人のための研究会Creative Literacy Lab - Exploring Further Potentials of Manga, Generative AI, and Pattern Languages
STEP 3:自分にぴったりの研究会の見つけ方 — 3つのアクション
自分の興味の方向性が見えてきたら、次は具体的なアクションに移りましょう。最高の研究会と出会うための3つのステップを紹介します。
アクション1:公式サイトとシラバスを「探検」する
気になる研究会を見つけたら、まずはSFCの公式サイトで担当教員のプロフィールや研究業績を調べてみましょう。さらに、オンラインで公開されている「シラバス(授業計画)」を読めば、その研究会が一年間で何を目指し、どのような活動を行うのか、より具体的に理解できます。
アクション2:オープンキャンパスやORFで「直接」話を聞く
SFCが開催するオープンキャンパスや、研究成果発表会である「ORF (Open Research Forum)」は、絶好の情報収集の機会です。各研究会がブースを出展しており、教員や在学生(先輩)に直接質問することができます。ウェブサイトだけでは分からない、研究会の「雰囲気」や「熱量」を肌で感じることが、何よりも重要です。
アクション3:自分の「問題意識」を「仮説」としてぶつけてみる
「この研究会に入れば、自分が探求したい〇〇というテーマを追求できるだろうか?」という仮説を立ててみましょう。そして、オープンキャンパスなどで教員や先輩に「私は〇〇という問題に関心があるのですが、こちらの研究会では、どのようなアプローチが可能でしょうか?」と、自分の考えをぶつけてみてください。その対話の中から、思わぬ発見や、本当に自分に合う研究会との出会いが生まれます。
最後に
SFCの研究会選びは、あなたの4年間の大学生活、そしてその先の未来をも左右する、大きな決断です。しかし、それは決して難しいだけの選択ではありません。150以上の多様な選択肢は、あなたの知的好奇心を刺激し、可能性を無限に広げてくれる「知のビュッフェ」です。
誰かが決めた「おすすめ」ではなく、あなた自身の心が「これだ!」と震えるような研究会を見つけ出すこと。その探求の旅こそが、SFCでの学びの第一歩です。さあ、あなただけの冒険を始めましょう。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。