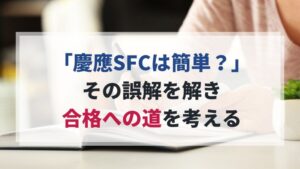こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
SFCと聞くと、プログラミングや社会問題解決といったイメージが強いかもしれません。しかし、SFCの学びの根幹には、独自の「デザイン」の概念が存在します。これは、単に美しいものをつくるだけでなく、社会の課題を解決し、未来を創造するための「X-Design」という先進的なアプローチです。
今回は、SFCが定義するこの「X-Design」に焦点を当て、それがどのように皆さんの学びや将来のキャリアに繋がるのかを徹底的に解説していきます。
SFCのデザインは「未知の領域」を拓くこと
SFCにおけるデザインは、まだ確固たる名称のない、未知のデザイン・研究領域(=X-Design)を開拓することにあります。この「X」には、異端(eXtreme)かつ実験的(eXperimental)に、領域を横断・乗算(Crossing, X)し、真の自己表現(eXpression)を行う、という深い意味が込められています。
これは、SFCが学生に求める「問題発見・解決能力」と「創造性」を、デザインという手法で具現化することを目指していることを示しています。SFCでは、学生が自由にプロジェクトに参加し、その過程で自らの専攻分野を創り上げていくことが重視されます。
SFCデザイン分野の4つのアプローチ
SFCのデザイン分野は、便宜上いくつかの領域に分けられていますが、これらは互いに独立したものではなく、自由に横断することが可能です。以下に、その代表的なアプローチを紹介します。
1. デジタル・ファブリケーションとアルゴリズミック・デザイン
コンピュータ・アルゴリズムやデジタル・ファブリケーション技術(3D/4Dプリンティングなど)を駆使し、これまでにないモノづくりに挑戦する分野です。建築を植物のように育てる、といった革新的な発想を、テクノロジーの力で形にすることを目指します。
2. 美術・ランドスケープ・コミュニケーション
美術、幾何学、環境デザインといった視点から、未知なる建築、都市、景観、そして「場づくり」をデザインする分野です。歴史や地域景観の探究を通じて、人と人とのコミュニケーションが生まれる新しい空間を創造します。
3. アート・サイエンス・パフォーマンス
芸術的な感性と、科学的な分析を融合させ、音楽や映像などの分野で唯一無二の自己表現を追求します。SFCには、音楽の神経科学など、科学的なアプローチで芸術を探求する研究室も存在しており、アートとサイエンスの境界を超えた研究が可能です。
4. 新たな循環デザインの開拓とまちづくりの実践
既存のリソース(廃材、粗大ゴミなど)を再利用・再編集し、新しい価値を生み出す「循環デザイン」を実践します。SFC周辺地域や自治体と連携しながら、実際のまちづくりに応用するプロジェクトに学生が参加できます。
最後に
慶應SFCのデザインは、単なるビジュアルデザインやプロダクトデザインにとどまりません。それは、あなたの問題意識やアイデアを、テクノロジーやアート、社会といった多様な視点と融合させ、まだ存在しない「未来」をデザインするための、最高のプラットフォームです。
SFCへの合格は、あなたの「デザインの志」を、このX-Designという最先端のフィールドで追求するための第一歩です。KOSSUN教育ラボは、皆さんがその志を明確にし、SFCの入試を突破できるよう、徹底的にサポートします。
あなたの自由な発想とデザインへの情熱を、SFCで形にしてみませんか?
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。