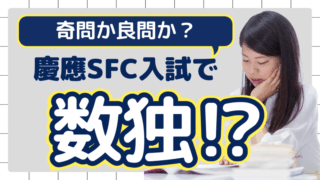
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「慶應SFCの入試に数独が出たらしい」という噂を聞いて、驚いた方もいるかもしれません。実際に、2013年度のSFC総合政策学部の数学の入試で、数独に似た問題が出題され、大きな話題となりました。
「勉強してきた知識が通用しない」「趣味のパズルで合否が決まるなんて不公平だ」といった声も上がりましたが、一方で、この出題にはSFCが受験生に求める「ある能力」を測る意図が隠されています。
今回は、この「数独問題」を例に、SFCが本当に評価する能力とは何か、そしてその対策法について徹底的に解説していきます。
SFCの「数独問題」が問いかけるもの
2013年に出題された数独に似た問題は、一般的な数学の公式や解法を暗記しているだけでは解けない問題でした。この問題は、受験生に以下のような能力を問うものでした。
1. 論理的思考力と問題解決能力
数独を解くには、論理的な推論を積み重ねる力が必要です。「この行にはこの数字がないから、このマスにはこの数字が入るはずだ」というように、与えられた情報から論理的に答えを導き出す能力が求められます。これは、SFCが掲げる「問題発見・解決型」の教育理念と深く結びついています。
2. 情報を整理し、全体像を把握する力
数独を解き始めるには、まず盤面全体を俯瞰し、どこから解き進めるのが最も効率的かを判断する必要があります。これは、複雑な状況の中から重要な情報を見抜き、全体像を把握する力を測るものです。
3. 柔軟な発想力とひらめき
数独が難しくなると、単純な論理だけでは解けない局面が出てきます。そのような状況を打開するには、固定観念にとらわれない柔軟な発想やひらめきが不可欠です。SFCが重視する「創造性」に通じる能力と言えるでしょう。
「数独」は奇問ではない? SFCの入試傾向
SFCは、この「数独問題」に限らず、既存の学問の枠を超えた、奇をてらった問題を出す傾向があります。
これは、SFCが単なる知識の暗記能力ではなく、変化の激しい現代社会で自ら「問い」を立て、解決策を創造できる人材を求めているからです。そのため、入試問題も、受験生が真の思考力を持ち合わせているかを見極めるために、独特な形式をとることが多いのです。
この傾向は、特にAO入試において顕著です。AO入試では、筆記試験の代わりに、あなたの「志望理由・入学後の学習計画・自己アピール」が評価されます。この書類には、あなたがこれまでの経験からどのような問題意識を持ち、SFCで何を学び、将来何を成し遂げたいのか、という「あなただけのストーリー」を表現することが求められます。
これは、まさに「数独問題」が問いかける「論理的思考力」と「問題解決能力」を、文章や図で表現する作業と言えるでしょう。
SFC合格のための「数独」的思考法
SFCへの合格を目指す皆さんにとって、この「数独問題」から学ぶべき教訓は、「表面的な知識の暗記に頼らず、思考の本質を鍛えること」です。
- 「なぜ?」を常に考える: 単に答えを覚えるだけでなく、「なぜこの答えになるのか?」「なぜこの問題が重要なのか?」といった「なぜ?」を常に問いかける習慣をつけましょう。
- 多様な情報に触れ、視野を広げる: 特定の分野に偏らず、新聞、雑誌、専門書など、多様な情報に触れましょう。異なる分野の知識を組み合わせることで、新しい発想やひらめきが生まれやすくなります。
- 「自分なりの答え」を導き出す練習をする: 与えられた課題に対し、常に「自分だったらどう考えるか?」「自分なりの解決策は何か?」という視点で、自分なりの答えを導き出す練習をしましょう。
最後に
慶應SFCの「数独問題」は、一見すると不公平な「奇問」に見えるかもしれません。しかし、その本質は、あなたが知識をどのように活用し、論理とひらめきを武器に、未知の問題を解決できるかを測る、SFCならではの「思考力テスト」でした。
この「数独」的思考法は、総合型選抜(AO入試)の出願書類作成や面接対策、そしてSFC入学後の学びにおいても、非常に重要な武器となります。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。


