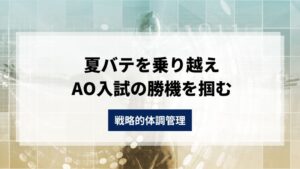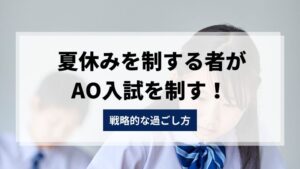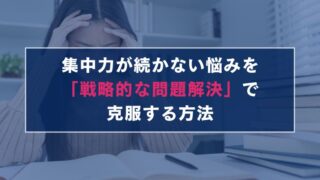
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
SFCのAO入試対策や一般選抜の小論文対策など、高い知的生産性が求められる中で、「集中力が続かない」「効率が悪い」という悩みは、受験生にとって深刻な問題です。
SFCの学びは「問題発見・解決」が核です。この「集中力が続かない」という状態も、SFC流に「解決すべき問題」として捉え直し、戦略的に克服することが可能です。今回は、集中力の低下を乗り越え、AO対策の質を最大化するための具体的な戦略を解説します。
1. 集中力が続かない原因のSFC流分析:外部環境と目標設定のズレ
集中力の低下は、意志力の問題ではなく、環境と目標設定が適切でないために起こります。SFCのAO対策では、特に以下の要因が集中力を奪います。
原因①:課題の「終わり」が見えない
AO対策の自己分析や志望理由書の構想は、「正解」がなく、どこまで深掘りすればいいかという「終わり」が見えにくい作業です。この不確実性が、脳に大きな負荷をかけ、集中力を分散させます。
- SFCの特性: SFCの課題は「問題発見」から始まるため、「完璧主義」は集中力の最大の敵になります。
原因②:外部環境の最適化不足(ウェルネスの欠如)
SFCは「心身の健康」が学問の前提であり、「ウェルネス科目」を設けています。しかし、受験期には、この「心身のウェルネス」がおろそかになりがちです。
- 体調管理の失敗: 特に夏場は、夏バテや睡眠不足が集中力に直結します。
2. 集中力を最大化する3つの戦略的解決法
「集中力が続かない」という問題を解決するために、以下のSFC流の戦略を実践しましょう。
戦略①:「時間の単位」を短く設計する(ポモドーロ・テクニック)
集中力が続かないなら、無理に長時間集中しようとせず、タスクを短く区切って完了させる達成感を積み重ねることが重要です。
- ポモドーロ法: 25分集中し、5分休憩を繰り返すなど、時間をブロック化して作業に取り組みましょう。これにより、脳への負担を減らし、「課題が終わらない」という感覚を打ち破ります。
戦略②:AO対策の「思考の切り替え」を意識する
AO対策では、「論理的思考」(志望理由の構成)と「創造的思考」(自由記述のアイデア出し)の切り替えが必要です。
- タスクの分離: 午前は「論理的思考」(書類のロジック修正)、午後は「創造的思考」(自由記述のビジュアル化)など、タスクの性質に合わせて集中する時間を分離しましょう。思考を切り替えることで、脳の異なる領域を効率的に使えます。
戦略③:「心身ウェルネス」を確保する
SFCの学生が実践するように、「心身の健康」を最高の知的生産の前提としましょう。
- リフレッシュ時間の組み込み: 勉強を「中断」する時間ではなく、集中力を「回復」させる時間として、短時間の運動や趣味の時間を意識的にスケジュールに組み込みましょう。
最後に
慶應SFCへの挑戦において、集中力の低下は「解決すべき問題」です。この問題を戦略的に克服し、AO入試の書類作成や小論文対策の質を最大化できる者こそが、SFCが求める「自立した問題解決者」となります。
あなたの集中力を最大限に引き出し、SFC合格を掴み取りましょう。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。