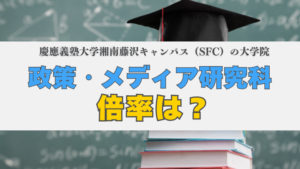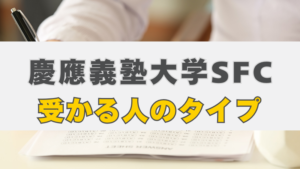- 1. 大学院は社会人の学びを歓迎している
- 1.1.1. 社会人コースの設置:働きながら博士号取得も可能
- 1.1.2. 実際の社会人学生の割合は? 公式データから読み解く
- 1.1.3. 社会人学生が多いことのメリット
- 1.1.4. 社会人学生が少ない可能性と、その背景
- 1.1.5. 進学を検討するあなたへ:まずは情報収集と個別相談を
- 2. なぜ総合型選抜があなたにとってのチャンスなのか?~3つのメリット~
- 2.1.1. メリット1:学力だけでは測れない「個性」と「熱意」をアピールできる
- 2.1.2. メリット2:早期に合格を掴み取り、入学までの時間を有効活用できる
- 2.1.3. メリット3:多様な価値観を持つ仲間と出会い、刺激的な環境で学べる
- 3. KOSSUN教育ラボのサポート体制
- 4. 最後に
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
「最先端の研究に身を置きたい」「これまでのキャリアをさらに発展させたい」――そう考える社会人の皆様にとって、大学院への進学は魅力的な選択肢の一つです。特に、社会の変革を担う人材育成を目指す慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科は、常に注目を集める存在でしょう。
しかし、いざ進学を検討するにあたって気になるのは、周囲の学生の属性、特に「社会人学生はどれくらいいるのだろうか?」という疑問ではないでしょうか。今回は、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科における社会人学生の実態について、そして、総合型選抜でSFCを目指すことのメリットについて、詳細に解説していきます。
大学院は社会人の学びを歓迎している
結論から申し上げますと、政策・メディア研究科は、社会人学生の受け入れに積極的に取り組んでいます。その証拠と言えるのが、一般入試(社会人出願)という入試制度の存在です。
この制度は、一定の職務経験を有する社会人を対象としています。これは、大学院が社会人がこれまでに培ってきた経験や知識、そして明確な研究意欲を高く評価していることの表れと言えるでしょう。
社会人コースの設置:働きながら博士号取得も可能
さらに、政策・メディア研究科の後期博士課程には、社会人コースが設けられています。このコースは、大学院修士課程を修了(あるいは大学学部を卒業)し、既に企業・官庁・研究教育機関等で5年以上の業績・経験を積み、問題意識を明確に持った社会人を対象にした、現在の職務を継続しながら博士号の取得を目指せる画期的な制度です。
これは、政策・メディア研究科が社会人のキャリア形成と研究活動の両立を真剣にサポートしていることを示す明確なメッセージと言えるでしょう。
実際の社会人学生の割合は? 公式データから読み解く
では、実際に政策・メディア研究科にはどれくらいの社会人学生が在籍しているのでしょうか?
慶應義塾大学が公式に公開している学生数のデータには、学部・研究科ごとの男女比などの情報はありますが、社会人学生の割合に特化した詳細な統計は見当たりません。
しかし、社会人コースが存在することを考慮すると、一定数の社会人学生が在籍していることは十分に考えられます。
社会人学生が多いことのメリット
もし政策・メディア研究科に多くの社会人学生が在籍しているとしたら、それは進学を検討する皆様にとってどのようなメリットがあるでしょうか?
- 多様なバックグラウンドを持つ仲間との出会い: 異なる業界や職種を経験してきた社会人学生との交流は、新たな視点や価値観を与えてくれるでしょう。
- 実践的な知見の共有: 社会人経験豊富な学生との議論は、理論的な学びをより実践的な視点から深める機会となります。
- キャリアネットワークの構築: 同じ目標を持つ社会人学生との繋がりは、将来のキャリア形成において貴重な財産となる可能性があります。
社会人学生が少ない可能性と、その背景
一方で、政策・メディア研究科は、学部からのストレートな進学者や、研究に専念するために進学する学生が多いという側面も考えられます。その背景には、以下のような要因があるかもしれません。
- 研究に特化した環境: 政策・メディア研究科は、最先端の研究活動を推進する拠点としての性格が強く、研究に集中したい学生が集まりやすい可能性があります。
- フルタイムでの研究活動の推奨: 大学院のカリキュラムや研究指導体制が、フルタイムで研究に取り組むことを前提としている場合があります。
しかし、これらの要因が社会人学生の受け入れを阻害するものではなく、それぞれの学生が自身のライフスタイルやキャリアプランに合わせて最適な学び方を選択できる環境が提供されていると考えるべきでしょう。
進学を検討するあなたへ:まずは情報収集と個別相談を
最終的に、政策・メディア研究科に社会人学生が多いか少ないかという点は、個人の感じ方や重視するポイントによって異なるでしょう。重要なのは、自身の学びたい研究分野やキャリア目標と、政策・メディア研究科の環境が合致するかどうかをしっかりと見極めることです。
そのために、まずは慶應義塾大学の公式ウェブサイトで入試情報や研究科の紹介を詳しく確認することをおすすめします。また、可能であれば、大学院の事務室に問い合わせたり、説明会に参加したりすることで、より具体的な情報を得ることができるでしょう。
なぜ総合型選抜があなたにとってのチャンスなのか?~3つのメリット~
ここからは総合型選抜で慶應SFCを目指す方に向けて、従来の学力試験とは異なる魅力を持つ入試方式である総合型選抜が、あなたにとっていかに大きなチャンスとなるのかを解説します。
メリット1:学力だけでは測れない「個性」と「熱意」をアピールできる
総合型選抜の最大の特徴は、書類審査や面接など、多角的な評価によって合否が決まる点です。これは、ペーパーテストの点数だけでは十分に表現できない、あなたの個性、これまでの経験、そして将来への強い熱意を大学に伝える絶好の機会となります。
- あなたの「好き」を活かす: SFCの総合型選抜では、「なぜSFCで学びたいのか」「SFCで何を研究したいのか」という明確な目的意識が重視されます。あなたがこれまで情熱を注いできた活動や興味関心を、SFCの学びとどのように結びつけ、将来どのような貢献をしたいのかを具体的に示すことで、強いアピール力を持つことができます。
- 主体的な学びの姿勢を示す: 高校生活で主体的に取り組んできた活動(生徒会、部活動、ボランティア、探究活動など)は、あなたの学びへの意欲や問題解決能力を示す重要な要素となります。これらの経験を通して何を学び、どのように成長したのかを、自身の言葉でしっかりと伝えることが大切です。
- 将来のビジョンを語る: SFCは、既存の枠にとらわれず、新しい価値を創造できる人材を求めています。あなたが将来、社会に対してどのような貢献をしたいのか、そのためにSFCで何を学びたいのかという明確なビジョンを持つことは、合格への大きなアドバンテージとなります。
メリット2:早期に合格を掴み取り、入学までの時間を有効活用できる
総合型選抜の多くは、一般選抜よりも早い時期に選考が行われ、合格発表も比較的早めに行われます。これにより、以下のようなメリットが生まれます。
- 精神的な安定: 早期に合格を得ることで、その後の受験勉強のプレッシャーから解放され、精神的に安定した状態で高校生活の残りの期間を過ごすことができます。
- 入学準備に時間をかけられる: 合格後、入学までの期間を、大学の授業で必要となる知識やスキルを身につけるための準備期間に充てることができます。SFCでは、入学前にオンラインでの学習プログラムなどが提供される場合もあり、スムーズな大学生活のスタートを切ることができます。
- 新たな挑戦への時間: 受験勉強に費やしていた時間を、自分の興味関心を深めるための活動や、新たなスキル習得のための時間に充てることができます。留学の準備を始めたり、プログラミングを学んだり、興味のある分野の書籍を読み込んだりするなど、可能性を広げるための貴重な時間となるでしょう。
メリット3:多様な価値観を持つ仲間と出会い、刺激的な環境で学べる
総合型選抜で入学してくる学生は、学力だけでなく、多様な個性や経験、そして強い問題意識を持っています。このような仲間たちと共に学ぶことは、あなた自身の視野を広げ、新たな価値観に触れる貴重な機会となります。
- 刺激的な学びの共同体: さまざまな背景を持つ学生が集まるSFCでは、授業内外で活発な議論が交わされます。異なる視点から意見を聞くことで、自分の考えを深めたり、新たな発想を得たりすることができるでしょう。
- ネットワークの構築: 大学生活を通して築かれる友人関係は、将来にわたってあなたの財産となります。総合型選抜で出会った仲間たちは、互いに刺激し合い、高め合うことのできる、かけがえのない存在となるはずです。
- 社会との繋がりを意識した学び: SFCは、社会の現代的な課題に積極的に取り組み、解決策を探求する学びを重視しています。多様な価値観を持つ仲間との協働を通して、社会との繋がりを意識した、より実践的な学びを経験することができます。
KOSSUN教育ラボのサポート体制
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜で SFC を目指す皆さんを総合的にサポートしています。
- SFCの入試情報提供: SFCのアドミッション・ポリシーや入試傾向、面接対策など、SFCの入試に関する情報を詳しく解説します。
- 書類作成指導: SFCの入試で課される志望理由書や自由記述などの書類作成を、個別に丁寧に指導します。
- 面接対策: SFCの面接官の視点に立った実践的な指導で、自信を持って面接に臨めるようにサポートします。
- 学習計画:一人ひとりに合わせた学習計画を作成します。
KOSSUN教育ラボで対応している対策の詳細は公式ホームページをお確かめください。
最後に
この記事が、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科、慶應SFCへの進学を検討されている皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。