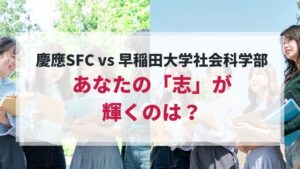こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
SFCの環境情報学部と総合政策学部のカリキュラムの中核をなすテーマの一つが「環境デザイン」です。この分野での学びは、単に建物を設計する「建築」に留まらず、都市、地域、さらには地球規模の課題を、「デザインの力」で解決することを目指します。
SFCの環境デザインは、建築・都市・地域レベルから地球レベルにわたるスケールの異なる幅広い視野で、持続可能な未来の環境デザインに関して、データ・エビデンスベースの実践的な教育・研究に取り組んでいます。
今回は、SFCが展開するこのユニークな「環境デザイン」の分野と、そこで身につく専門性について解説します。
1. SFCが定義する「環境デザイン」の4つの領域
SFCの環境デザインは、学生や教員が所属する「専攻」や「コース」ではなく、現在の研究領域を便宜上わかりやすく束ねた編集上の区分として、以下の4つの領域に分類されています。
1. 建築環境デザイン
- 内容: 建築空間のデザイン、構造のデザイン、生産手法など、建築の空間に関わる環境を意識した実践的な研究です。IT技術の応用なども取り入れられます。
- 専門性: 一級建築士試験を受験できる授業体系となっており、実社会に展開するための構築方法やデザイン手法を深く学べます。
2. 地域環境デザイン
- 内容: リモートセンシング、IoTによるフィールドセンシング、地理情報システム(GIS)、気象・気候解析などの空間情報技術やデータ分析技術を活用します。
- 専門性: 災害リスク適応や地域活性化の要請を捉えた、脱炭素型社会や持続可能なまち・地域デザインの支援に取り組む力が身につきます。
3. 都市環境デザイン
- 内容: 都市の歴史や文化・文脈を読み解きながら、まちづくり、地方地域再生、生態環境や防災システムなどの視点も加えます。
- 専門性: 都市や地方の環境の創造と保全を通じた、安全で豊かなハードとソフトの環境デザインの研究と実践に取り組みます。
4. 地球環境デザイン
- 内容: 地球規模の技術革新や国際的な協調関係の構築などを通じて、人新世時代に突入した人類が直面する気候変動や環境破壊といった巨大な課題に取り組みます。
2. 環境デザイン分野の核心:「自由にプロジェクトに参加し、自らの専攻分野を創る」
SFCの環境デザイン分野の最も重要な特徴は、学生が「自由にプロジェクトに参加し、結果として自らの専攻分野を創っていく」という点です。
これは、SFCの「問題発見・解決」という教育理念と直結しています。
- 学際性: 自分の興味が「建築」と「IT」の融合にあれば「建築環境デザイン」と「情報技術」の科目を自由に組み合わせて履修します。
- 実践性: 研究会やプロジェクトを通じて、理論だけでなく実社会に通用するデザインや技術を身につけます。
- データ・エビデンスベース: 創造的なデザイン能力だけでなく、データ分析に基づいた論理的な根拠(エビデンス)を持って問題を解決する能力を養います。
最後に
慶應SFCの「環境デザイン」は、単なる美的なデザインではなく、持続可能な未来を構想し、それを実現するための論理的かつ実践的なデザイン力を意味します。
AO入試においては、あなたがどのような環境問題に強い関心を持ち、このデザイン力をどのように活用してその問題を解決したいのか、という「志」が強く問われます。
KOSSUN教育ラボは、皆さんがSFCの先進的な環境デザインの学びを深く理解し、合格を掴み取れるよう、徹底的なサポートを提供します。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。