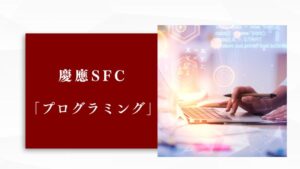こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
SFC(湘南藤沢キャンパス)の学びの核は、「問題発見・解決」を実践する「研究会」にあります。この研究活動において、学生一人ひとりの成長と研究を最も身近で支える存在が「メンター」(指導教員)です。
SFCにおけるメンター制度は、単なる指導者と学生の関係を超え、学生の自律的な挑戦を支える協働的なパートナーシップを意味します。今回は、SFCのメンター制度の役割、そして指導体制の特徴について解説します。
1. メンター制度の役割:研究と人生の「対等なパートナー」
SFCのメンター(指導教員)は、学生が自らの「志」を学問的に深め、最終的に「卒業プロジェクト」として結実させるまでの過程を、一貫してサポートします。
役割①:卒業プロジェクトの指導
SFCでの学びの集大成である「卒業プロジェクト」の担当教員を「卒プロメンター」と呼びます。
- 対話を通じた研究推進: 卒業プロジェクトは、通常2学期間以上かけてメンターとの対話を行いながら進められ、論文や作品など実際の結果物を作成し、評価・認定を受けます。
- 学術的な支援: メンターは、あなたの研究テーマの学術的妥当性や、研究手法について指導し、卒業プロジェクトの成功へと導きます。
役割②:研究会を通じた「対等な協働」
SFCの教員は、研究会において、学生に一方的な知識伝授を行うのではなく、学生を「対等なパートナー」として期待しています。
- 協働の精神: 教員の経験や人脈と、学生の発想やパワーの両方が先端研究には欠かせないという考えのもと、教員と学生が協力して研究活動を推進します。
2. メンター制度の戦略的な役割:「アスペクト」という道標
SFCのカリキュラムは、学生が自分に合ったメンターを見つけるための独自の仕組みを導入しています。
「アスペクト」によるマッチング支援
SFCでは、教員や授業科目の研究領域を構成する諸側面を「見える化」した「アスペクト」という仕組みがあります。
- 発見の道標: アスペクトを道標にすることで、学生は自分の関心あるテーマに沿って、これまで視野に入ってこなかった研究会や、思わぬ分野の教員(メンター)を「発見」することができます。
- 卒プロ申請の条件: 卒業プロジェクトのメンター申請を行うためには、直前の学期までに、メンターの指定するアスペクトを充足していることが条件となっています。これは、メンターとの研究領域が一致しているかを測る重要なステップです。
3. AO入試戦略:「メンター」への強い志望を証明する
SFCのAO入試に挑戦する受験生にとって、将来のメンターを見据えた「志」の表明は非常に重要です。
- 提出書類での言及: 志望理由書や学習計画書の中で、あなたが指導を受けたい特定の教員(メンター候補)や研究会に言及し、その研究テーマとあなたの「志」がどのように合致しているかを具体的に論述しましょう。
- 対話のポテンシャル: 面接では、メンターとの対話を通じて研究を進める「協働性」と「対話力」が評価されます。あなたのアイデアを論理的かつ情熱的に伝えられるか、という「対等なパートナー」としてのポテンシャルを証明しましょう。
最後に
KOSSUN教育ラボは、あなたの「SFCで学びたい」という熱い想いを、最も効果的な形でSFCに届けるお手伝いをします。まずは一度、無料相談にお越しください。あなたの個性や強みを活かし、慶應SFCへの合格を掴み取るための具体的なロードマップを一緒に考えていきましょう。
KOSSUN教育ラボは、慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)の総合型選抜(AO入試)に特化した対策を行っています。受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。慶應SFCをはじめ、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。